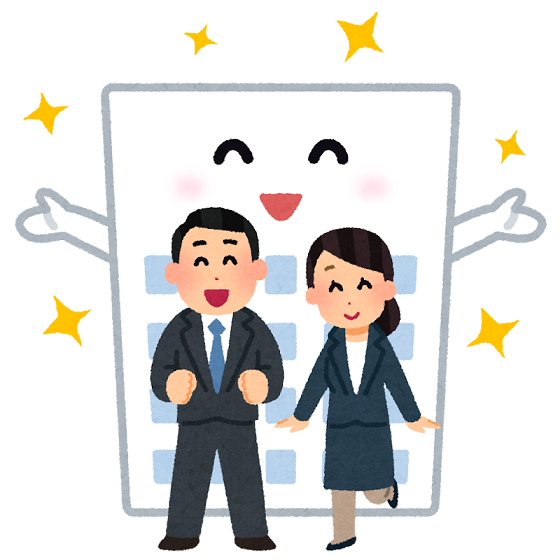就活/ 就職活動の面接でよく質問される「最近読んだ本は何ですか?」に模範解答はあるの!?
就職活動の面接でよく質問される「最近読んだ本は何ですか?」に模範解答はあるの!?
就活/就職活動中の面接でよく聞かれる質問の1つとして、「最近読んだ本は何ですか?最近読んだ本について説明してください。」というものがあります。
就活/就職活動中の
就活生の皆さまの中には、「最近読んだ本は何ですか?」という質問に対する模範解答は何だろう?と疑問に感じている人も少なくないのではないでしょうか!?
そもそも、就活/就職活動中の面接で、面接官が「最近読んだ本は何ですか?」と質問する際の意図・目的とは何でしょうか?
もちろん、就活/就職活動中の面接で緊張している
就活生の緊張を解きほぐしてリラックスして面接に臨んでほしいという意図・目的でそのような質問をしていることもありますが、基本的には説明能力やコミュニケーション能力、自分の意見や思いを相手に対して説得力がある形で伝える能力がどの程度あるのかを見ているものです。
就活/就職活動を終えて実際に就職すると、どのような業界、企業、組織であれ、自分たちの商品やサービス、自分たち自身のことについて、相手に対してわかりやすく説明することを求められる場面が頻繁にあります。
そういった場面で、どれだけ情熱と説得力が感じられる説明ができるかどうかは、その人の実力や評価、仕事の成果に直結します。
![]()
![]()
採用側は、そのような説明能力を確認したくて「最近読んだ本は何ですか?」という質問を就活生に対してするわけですので、説明をする
就活生側としては、自分が全く興味の無いようなジャンルの本や難しい内容の本について見栄を張って話す必要は全くありませんし、本当に自分が最近読んだ本について自分の言葉で説明すれば良いのです。
たまに、漫画やエンターテインメント性の高い本を事例として挙げてはいけないと言われることもありますが、実際には自分が情熱を持って説得力のある説明ができるのであれば、漫画やエンターテインメント性の高い本も含めてどんなジャンルの本でも構いません。
ひと昔前であれば、「最近読んだ本は何ですか?と聞かれて、漫画やエンターテインメント性の高い本について説明するなんて非常識だ」と思うような面接官も中にはいたかもしれません。でも、個性や多様性が重視される現代社会では、むしろ普通の人が選ばないような本を選んだ理由、その本の内容と魅力、その本から学んだことなどを、情熱を持って説得力がある形で説明できることで、採用側からの評価がぐっと高まる可能性があります。
ただし、「最近読んだ本はありません」と回答してしまうと話がそれだけで終わってしまうので、その時々のベストセラー本でも自分の興味があるジャンルの本でも何でもよいので、最近読んだ本について話せるように読んでおくことをおすすめします。
そのうえで、以下の点について簡単に整理して、いつでも短時間でポイントを絞って話せるように準備しておくと安心です。
- 本のタイトル/題名(できれば著書名も)
- その本を読もうと思った理由/背景
- その本の概要/ポイント
- その本を読んで思ったこと/学んだこと
- その本の魅力(他の人に薦めるのであればその理由)
株式会社アスパークが提供している適性テストをもとにAIが自分に合った企業を見つけてくれる就活アプリ:【Lognavi】
 を活用して、ご自身と相性が良い企業を探してみませんか?
を活用して、ご自身と相性が良い企業を探してみませんか?
就活/
就職活動中の
就活生の皆さまの中には、ご自身と相性が良い企業がどこなのかわからないというお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
なんとなく大手が良いというイメージがあるから大手企業の採用選考を受けたり、とりあえず周りに合わせておこうという気持ちで周囲の人たちに人気のある企業の参考を受けたり、特に理由はないけれ江戸親や家族が勧める企業の選考を受けたりという就活生の皆さまは少なくありません。
また、なんとなく安定してそうだからメーカーに就職したい、なんとなく将来も伸びそうだからIT業界に行きたい、なんとなく人と関わるのが好きだから人材業界に行きたい、といった形で志望企業を決める就活生の皆さまも数多くいらっしゃいます。
そういったやり方で就活/
就職活動を進めるのも決して悪いことではありませんが、後悔することの少ない
就活/
就職活動をするためには、自分に本当に合った企業がどこなのか、このタイミングで改めて真剣に考えてみても良いのかもしれません。
「自分に合った企業ってどんなところだろう?」「自分が活躍できる企業ってどんなところだろう?」「 自分の強みや弱みってどんなところだろう?」「就活ってどうやって進めれば良いんだろう?」「自分の価値観に合った企業で働きたい・・・」「なんとなく大手を見ているけど、この先何があるか分からないから不安・・・」そんな風にお考えの就活/
就職活動中の
就活生の皆さまにおすすめなのが、就活のリアルが分かる学生限定就活SNS!【Lognavi】
![]() です。
です。
![]()
【Lognavi】
![]() は、適性テストをもとにAIが自分に合った企業を見つけてくれる就活アプリです。企業で活躍しているエース社員と、
は、適性テストをもとにAIが自分に合った企業を見つけてくれる就活アプリです。企業で活躍しているエース社員と、就活/
就職活動中の
就活生の皆さまに同じ適性テストを受験していただき、テスト結果をもとにAIがご自身に合った企業をマッチングしてくれます。
適性テストの結果から、就活/
就職活動中の
就活生の皆さまに相性が良い企業が上位表示されるようになるほか、入社後のミスマッチをなくすためにも「業界」だけではなく「思考性」をもとに
就活/
就職活動をサポートしてくれます。
また、【Lognavi】
![]() は、大手からベンチャーまで600社以上に導入されており、適性テスト受験後のスカウト受信率は99%以上と、受験した
は、大手からベンチャーまで600社以上に導入されており、適性テスト受験後のスカウト受信率は99%以上と、受験した就活/
就職活動中の
就活生の皆さまがほぼすべてがスカウトを受けています。
実際、多くの有名企業や人気企業が【Lognavi】
![]() を利用しており、具体的には、
を利用しており、具体的には、ダイハツ工業、
カシオ、
フジテック、
毎日放送(MBS)、
コメリ、
スズキ、
シャトレーゼ、
ホンダ、
ベストブライダル、
伊藤忠商事、
関西テレビ放送(カンテレ)、
日清食品、
大林組、
東京インテリア、
丸大食品、
アイシン精機、
井村屋グループ、
プリマハム、
フジテレビ、
伊藤ハム、
アイ・ケイ・ケイ、
テレビ西日本(TNC)、
三幸製菓、
湖池屋、
ノバレーゼ、
読売テレビ(ytv)などがこのサービスを使っています。
![]()
【Lognavi】
![]() のご利用の流れはとても簡単です。
のご利用の流れはとても簡単です。
まず、【Lognavi】
![]() をダウンロードし、ご自身の基礎情報を入力して会員登録を完了させたうえで、適正テストを受験します。
をダウンロードし、ご自身の基礎情報を入力して会員登録を完了させたうえで、適正テストを受験します。
適正テストは、下記のような簡単な質問に答えるだけですので、何かと忙しい就活/
就職活動中でも負担にならないはずです。

適正テストを受験し終えると、ご自身と相性の良い企業がいくつかピックアップされて表示されます。

あとは、そういった企業にご自身のほうからアプローチしてみるのも良いですし、そういった企業からのスカウトを待つこともできます。
「自分に合った企業ってどんなところだろう?」「自分が活躍できる企業ってどんなところだろう?」「 自分の強みや弱みってどんなところだろう?」「就活ってどうやって進めれば良いんだろう?」「自分の価値観に合った企業で働きたい・・・」「なんとなく大手を見ているけど、この先何があるか分からないから不安・・・」そんな風にお考えのそんな風にお考えの就活生の皆さまは、【Lognavi】
![]() をチェックしてみてはいかがでしょうか!?
をチェックしてみてはいかがでしょうか!?